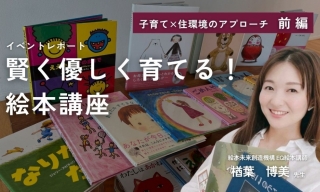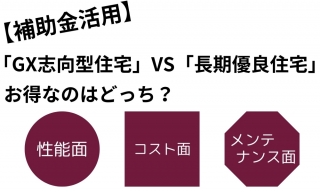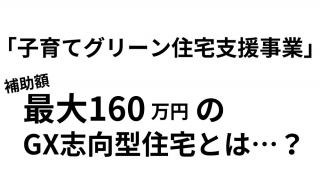「子どもの可能性を広げる絵本の読み聞かせ」イベントレポート
後編 絵本未来創造機構 EQ絵本講師 楢葉 博美先生 スペシャルトークセッション
「知育が変える家づくり」
2025年04月05日

前編・後編でお届けする「子どもの可能性を広げる絵本の読み聞かせ」イベントレポート。前編では、絵本未来創造機構 EQ絵本講師 楢葉 博美先生による「絵本講座」、一般社団法人 日本人の健康をつくる住宅断熱リフォーム推進協議会 事務局長 コマツアキラ氏による「お家の間取りとインテリアコーディネート講座」についてご紹介しました。後編では、弊社取締役社長 上田 公平と楢葉先生によるトークセッションの様子をお届けします。トークセッションのテーマは「知育が変える家づくり」ソフトウェア(知育)がハードウェア(住宅環境)に与える影響、またハードウェア(住宅環境)が知育に与える影響について絵本講師として活躍をされながら、三児の母でもある楢葉先生へお話しを伺いました。
トークセッション スペシャルゲスト

楢葉 博美先生
三兄弟の育児を絵本に助けられたことがきっかけで、イライラからニコニコになれる方法・短所が長所に変わる声かけを絵本を通して実践。1日5分からの絵本読み聞かせで、子どもの頭も心もぐんぐん育てながら、お母さん自身が自分を大切にしながら理想の育児・人生を叶えていく方法を、絵本を通してお伝えしています。
トークセッション HASI HAUS取締役社長 上田 公平

知育と家づくりのつながり
ーソフトウェア(絵本読み聞かせ)とハードウェア(住宅環境)一見関係がなさそうな知育を家づくりに取り入れようと思ったその背景は何でしょうか?
上田
家づくりは家庭づくりだと思っています。お客様は「子どもが生まれたから家を建てたい」とおっしゃいます。でも、その家づくりが本当に子どものためになっているかというと、必ずしもそうではないんです。自分のこだわりや理想も大切ですから。
しかし「どんな子どもに育ってほしいか」という想いが根底には確かにあるのも事実。性能や換気などの様々な要素が子育てに影響を与えるのを見て、改めて「子育ては家づくりと直結している」と感じたからです。
親の自己肯定感が子どもを育むー親と子どもの成長を支える住環境
ー家づくりとは家族づくりであり、家庭づくり。そこを第一に考えるべきだが、自分自身を大切にすることも同様に重要だと思います。楢葉先生がそこにお気づきになられたきっかけは何でしょうか?また知育という考え方と住宅環境のつながりについても教えてください。
楢葉先生
自分の経験にも影響していますが、特に女性は子どもが生まれると自分を後回しにしがちです。そして「子どものためにやっているのに、なぜか満たされない」という気持ちを抱えている方が多い。
最初は子どもの自己肯定感を高めたくて学び始めた絵本でしたが、学びを深めていく中で、親の自己肯定感が子どもの自己肯定感に密接に関わっていることに気が付きました。
親が満たされていれば、子どもにも余裕をもって接することができ、長所にまで目が向けられるようになりますから。
そしてソフトウェア(絵本読み聞かせ)だけでなく、ハードウェア(住宅環境)からもアプローチしていけるというのはとても良いと思います。
上田
知育を考えた家づくりを行う時に、大切なことが「換気、断熱、間取り」です。換気設備の整った住宅は子どもの集中力に影響を与える他、睡眠の質が良くなるというデータもあります。
また、断熱が良い住宅は、子どもの疾病率が約36%減少すると言われています。
さらに、子どもが自然にお手伝いをできる動線を考えた設計は、助け合い精神を育む上で非常に重要。例えば、キッチンや洗濯など家事をするスペースへのアクセスを子どもがしやすいように工夫すると、日常的に親の手伝いをする機会が増えます。これにより、子どもは「自分も家族の一員として役に立っている」という自身を持ち、自己肯定感が高まります。

家族みんなで家を育てるー新しい住まいの形
ーしかし、実際は「家事は母親の仕事」という意識が根強く残っている家が多いですよね?
家事動線を意識することは良いですが、母親一人に負担をかける間取りになっていることもあります。
そういった場合にはどのようにアプローチしていくのが良いのでしょうか?
上田
実際に住む人が「働きやすい」「便利だ」と感じる間取りを作れば、自然と家事も分担できるようになります。
そしてそれができるのは、間取りを考える段階。家族で協力するという視点を最初から持っておくということがとても大切だと思います。
それに、そういう視点を住宅会社側が持っておくということも重要。そうでないと「母親が家事をしやすい間取りを提案して終わり」ということになってしまいかねません。
そうではなくて、家族みんなで家事を協力しながらこなせるような間取りをこちらからご提案できるようになる必要があります。
楢葉先生
そうですね。時代と共に求められるものが変わってきていると思います。男性も家事をする時代だからこそ、「奥さんの好きなキッチンを決めさせてあげる」のではなく、みんなで協力できる環境を整えることが大切ですよね。
上田
リビングの役割も変わってきています。かつては、家族が集まって同じものを見て楽しむ場所でしたが、今ではリビングに集まっていても、個々にスマホを楽しむ時代です。
だからと言って、「家族が集まれるリビングは必要ない」という話ではありません。大切なのは両親の「うちの家族はこう過ごしてほしい」という想いを間取りに組み込むこと。
家族の在り方を考え、意図的に反映させることが、住宅会社の役割だと思っています。

家族の未来を育む家づくり
ー最後に、知育という観点を家づくりに取り入れることで、お客様にどのような価値を提供できと思いますか?
上田
私たち工務店は建築を生業としていますが、お客様にとって住宅は人生最大の買い物です。ローンを組んで毎月返済していくわけですが、これは「投資」でもあるんです。自己実現のための投資ですね。
知育という観点で家づくりを考えることは、これまであまり意識されてこなかったかもしれません。しかし、これからは「どんな家庭を築くか」という視点で間取りを考える必要があります。子育てや生活をもっと楽しく、豊かにする家づくりができれば、「投資」以上のものを提供ができ、またお客様も満足して暮らしていっていただけると思っています。
対談を終えて
トークセッション通じて「知育の視点で始める家づくり」について道筋が示せたのではないかと思います。そして、我々の業界がこれからの未来を創っていく上で、重要な存在であることも再確認できました。刻一刻と変わる住宅業界の中で、常に最新の情報を取り入れ、また多角的な視点を取り入れた家づくりをし、最適な住宅をお届けできるよう、努力を続けてまいります。
「未来の子どもたちのために」ー住環境が果たす役割を改めて考え、より良い暮らしを提案することの大切さを実感するセッションとなりました。